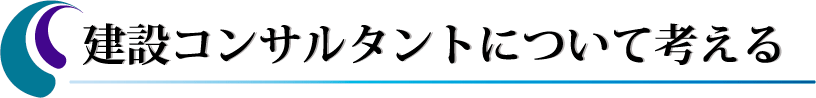欧米の公共工事は、下請け率は低く、自社の施工率が高くなっています。
その理由について、解説します。
①小工区分割発注
欧米の場合、多数の工種がある大工区を一括発注するのではなく、小工区分割発注が基本です。
その理由は、小工区の方が工種が少なく、地元の中小建設企業でも参加できるため、入札参加者が増える→競争激しくなる→価格が下がる と発注者が考えているからです。
また、工種が少なければ、それを専門とする工事会社が、入札に参加しやすくなり結果として、自社施工率が高くなります。
②人材の流動性が高い【解雇が容易】
建設事業は、繁忙期と閑散期があり、また工事受注の可否で年単位での受注額も大きく変動します。
そうした中で、ピーク時に合わせて自社施工の人材を社内に常時雇用で多数抱えるとなると、閑散期は仕事がないのに、給与は払わないといけないため、企業経営への大きな負担になります。
そのため、社員を簡単に解雇できない日本では、社内で人員を抱えず、下請けを使い、流動化します。下請けもまた、孫請けと同じ行為を繰り返し、重層化し、最後は、一人親方まで行きつく、生活の不安定性は、最末端の個人の職人に押し付けられるような構造となっています。
欧米の場合、解雇も容易で、工事期間のプロジェクト単位での雇用もできるので、直接雇用に対するリスクが低く、結果として直接施工比率が高くなると考えられます。
末端の職人等の、生活の不安定性は、欧米も同様といえるかもしれません、無駄な中抜きされない分、建設コスト、技術者の報酬の両面で、欧米の方が合理的に見えます。
③自社施工高比率の規則
建設工事が元請け下請けの重層化すると、中抜きが発生し、建設事業のコスト増になります。
そのため、発注者によっては、自社施工比率の規則が設けられています。
カルフォルニア州のように自社施工比率が50%以上が規則
以上の3つの理由により、欧米は、自社施工比率が高くなっていると考えられます。
ちなみに、日本の元請けのゼネコンは自社施工部門は、ごく小規模で、5次下請けくらいまで重層化(通称:中抜きジャパン)している理由は以下を参考にしてください。
参考コラム:社会構造は法制度によって作られる