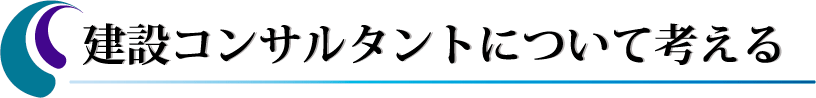日本の場合は、昔は、完成保証人が必要でしたが、指名競争および完成保証人制度が、新規参入を阻害し、談合の温床の原因となると言われ、完成保証人制度を廃止され、現在は、建設業保証株式会社などの、保証証券を提示したりします。
※ちなみに保証料率は、保証株式会社のホームページを見る限り破格の安さです。
欧米の場合は、完成保証について解説します。
まず、米国の州の公共工事においては、ボンド(保証証券)が一般的です。
完成保証については、全体工事金額の50%の保証証券の提示が求められます。(カルフォルニア)
その他、ヨーロッパ各国については、留保金という形が主流です。
日本のODA(円借款)によるインフラ工事も同様で、国際的には、留保金方式が主流であると考えられます。
具体的な方法ですが、欧米の公共工事はユニットプライス方式で、工種の工事単価を契約しておいて、毎月で工事出来高数量に合わせて、支払いが行われます。
行政は、毎月の支払金額から、留保金を差し引いた金額を支払います。
留保率は、支払金額の5~10%くらいの範囲です。
留保率が10%の場合の例で説明すると
毎月の支払いから10%を差し引いた金額を業者に支払い、行政側は10%の留保金を確保します。
そして工事が無事完成した場合、完成時に留保金全体の半分(業務金額の5%)を支払います。
残りの5%は2年間の瑕疵担保保証の留保金として留保します。
完成供用の一年後に2.5%、そのまた1年後に最後の2.5%を支払います。
※あくまで一例です。
留保制度は、業者側は、保証証券を用意しなくても良い点は、メリットですが、完成後に業務金額の5%の支払いを留保されるのは、業者側の経営利益的には、厳しいものがあります。
ちなみに、完成保証金が使われる可能性があるケースとは、以下のようなケースが考えられます。
・工事中に、不良工事が発覚し、業者に完成能力がないと認定された場合
・業者が他の工事を優先し、工事が止まってしまう場合
・工事期間中に請負業者が倒産した場合
このような場合、契約解除し、代わりの業者と契約する必要があります。
このような事態に対するコストが、業務金額の5~10%の留保金では足りないだろうと思うかもしれません。
欧米の場合は、設計者が直接施工監理(ザエンジニア)し、常時検査で施工出来高数量で、毎月支払いをするので、こうした異常は、傷口が大きくなる前に発覚します。
リスクが細かく、分割されているので、こうした事態にも対応可能なようです。
また、日本的感覚では、勧善懲罰的な発想で、悪徳業者を許さないために、保証率を上げたり、瑕疵担保期間を10年等にすべきと考えがちですが、もし、そのような保証を業者側に要求すると、業者側は、事業リスクが増大して、そのリスク分、入札価格を増大させる行動を取ります。
業者側にリスク負担を過大に要求した結果として、建設コストが増大してしまいます。
留保率10%、瑕疵担保期間2年というのは、考えられる保証の最大値とされているようです。(日本のJBIC(国際協力銀行)の入札ガイドラインも同様の認識)
実際に、不良工事等の事態を経験したか、欧米の発注者に尋ねましたが、皆、そうしたことは経験したことがないとのことでした。
※紛争仲裁機関等に行けば、データはあるかもしれません。
日本の場合、前払い金4割、完成検査後に残り6割という支払い方式においては、例えば、前払い金を受け取って、倒産とか、完成時に不良工事発覚で、再施工を命令したものの経営破綻等が起こった場合、かなり問題になるので、完全保証の証券が必要かもしれせん。
※リスク管理的に、かなりバランスが悪く見えます。
しかし、保証料率が格安で、保証会社の経営が成り立っていることを考えると、そうしたケースは実際は、ほぼないということになり、それなりに機能はしていると言えそうです。