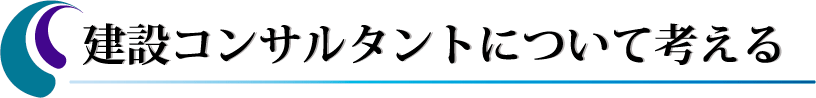入札時に予定価格を入札金額が超過し、入札不調になった場合の対応ですが日本では金額だけ書いた紙を入札し、1回目不調の場合、すぐに2回目の入札を行います。
それでも不調の場合3回目の入札を行い、3回目も不調の場合、最低価格の業者と随意契約等の交渉をするか、予算の見直しするかの流れが一般的です。
日本の場合は、契約範囲等の変更はなく、その場で業者に、根拠なく入札金額の値引きを要求する点が特徴的です。
昔、指名競争中心の地域においては、2回目不調になると、指名業者間でくじ引きして、誰が大幅値引きして落札するかを決める。行政のプライドを保つためと称して、そうした調整が行われていると聞いたことがあります。
今は、さすがにやっていないと思いたいですし、公共工事の入札不調が増えていると聞きます。
欧米の場合、予定価格にプラスして予備費を確保している発注者も、そうでない発注者もありますが、ここでは予備費がないケースを想定します。
欧米の公共工事は、ユニットプライス方式入札という、計算表(工種×数量×単価の一覧表)を入札するのが主流です。
※参考:ユニットプライス方式入札とは
予定価格を入札価格が超過した場合、行政の想定している工種の単価と各入札業者の工種単価を比較して、認識に違いがないか確認します。
行政側と業者側に工種のレベルに認識の違いがあった場合、説明し、業者は訂正することができます。
それでも、予定価格を超過する場合は、その場で、入札は不調となります。
その後は、行政側の工種単価の認識を訂正し、新たな予定価格を設定するという方法がありますが、その場合、議会等での新たな予算承認が必要になり、事業が遅れる可能性もあります。
そこで、発注範囲の見直しして、工区延長の短縮や、特定工種を削除して、予算内に収まる工事として、再度入札を行うケースが多いようです。
※日本のように、その場で値引きを求める再入札をすることはありません。