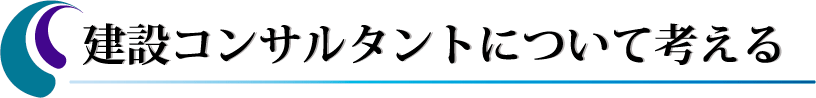日本の入札は、予定価格に対して低入札になった場合、ダンピング(原価以下の落札)を疑い、都道府県の工事等では最低制限価格となると自動的に失格になったり、国の場合は、低入札調査が入ります。そうすると、業者側は、かなり面倒くさいことになるので、その前に業者側から辞退するケースが多いそうです。
欧米の場合も、予定価格より著しく低い金額だったり、あるいは入札内容について、不正が考えられる場合は、調査を行いますが、日本の場合とは、だいぶ趣旨が違います。
欧米の公共工事は、ユニットプライス方式なので、入札は、工事費計算表(工種と数量の一覧表に、工事単価を記入し、各工種の工事費を算出し、それを合計した金額を記入)を入札します。
金額を書いた紙を入札するだけの日本と違い、欧米の場合、入札された計算表を見れば、入札業者が、各工種単価をいくらで想定しているかが、分かります。
そこで、発注者は、自分達の積算した予定価格の計算表と、各入札業者(複数業者)の計算表から、各社の想定する工種単価のばらつきや、行政側の想定との違いが分かります。
行政側が考える工事単価と比べて、異様に金額が高かったり、低かったりした場合は、行政側が、業者に認識の違いがないか確認します。
工種単価に対して、行政側と入札業者側の認識の違いがあった場合は、入札業者側はそれを修正することが認められています。
※日本の場合、一度入札した金額を後から変えることはできません。
仮に、予定価格の50%で入札した業者があって、行政が、その工事は、本当にその金額でできるか業者に確認し、業者が「うちは、その単価でできます」と答えた場合は、その業者が落札します。
行政側は、利益が出ない金額で業者が入札するわけないと考えていますし、発注図面・仕様のものが施工できる業者であれば、安ければ安いほどよいと考えています。
また、欧米の場合は、設計者が施工監理し、監理者の常時検査の月々の出来高払いであり、さらに完成保証担保も留保しているので、仮に工事中に不良工事が発覚しても、ダメージを最小化できるリスク管理の仕組みがあるためと考えられます。
欧米の発注者が警戒する入札不正は、「アンバランス・ビッド」と呼ばれるものです。
土木工事は、一品生産であり、また、測量図や地質データは、完璧ではありませんので、現場と図面とは、必ず誤差があります。
日本の場合は、この誤差を、「建設コンサルタントのレベルが低い、設計ミス」と決めつけて、設計変更で対応しますが、行政に予算がない場合、ゼネコンが持ち出しで泣くことになります。
欧米の場合は、図面と現場が違うことを前提としたシステムで出来ており、設計者が施工監理し、現場と図面の違いについても、設計者=監理者として柔軟に対応できますし、各工事の単価(延長や㎥など)で契約しており、現場条件に合わせて、数量が変わっても、実際の施工出来高に合わせて支払うので、柔軟かつ双方に損のないやり方となっています。
「アンバランス・ビッド」は、現場と図面が異なり、出来高払数量が変わることに目を付けた不正です。
業者側は、実際の施工時の出来高数量が大幅に増大しそうな工種の単価を高額にしておいて、その他の工事単価を安くして、合計金額を下げて、落札します。
そして、施工時、実際の出来高数量が増大するので、そこで稼ぐことができます。
例として、地盤改良や基礎工事など、掘ってみないとわからない部分については、そうした手で稼ぐことができます。
また、工事初期工程の工事単価を高くして、出来高月払いで、工事当初に大きく稼ぎ、後半は適当に仕事するようは悪徳業者もあるようです。
行政側は、入札において、このような「アンバランスビッド」を警戒しています。