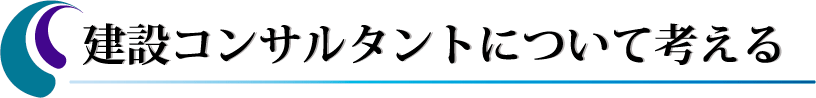欧米の場合、ユニットプライス方式入札が主流で、数量総括表の各工種に対して、単位当たりの工事単価を記入し、各工事費を算出し、それを合計して、総工事費を算出した紙を入札します。
※参考:ユニットプライス方式入札とは
そのため、欧米の発注者は、過去の工事の入札参加企業の施工単価の膨大なデータを保有しています。
欧米における工事積算は、各工種の入札単価実績値(例、過去二年の平均値等)を用い、発注に用いる数量表に入れて、工事費を算出し、それが、予定価格になります。
特殊な工種でデータがない場合は、周辺の発注機関(隣の州など)に問い合わせる。積み上げ方式で積算する。複数業者から見積もりを取るなどの対応をします。
特に決まった積算基準はありません。
入札業者側も、過去の自社の施工単価実績データを蓄積しており、入札に際して、図面や、現地状況を勘案しながら、数量表に単価を入れて積算し、それが入札価格になります。
※下請けを使う部分は、下請けから見積もりを取ります。
入札は、上記の数量表ごと入札し、合計金額が最低の業者が落札します。
このように欧米の場合は、過去の入札単価データをそのまま使うので、発注者、入札者双方にとって、非常にシンプルで簡易な積算をしています。
一方で、日本の場合は「積み上げ方式」と呼ばれるやり方で積算します。
各工種の材料費、施工費を積み上げて、直接工事費を算出し、間接費を上乗せして総工事費を算出するやり方です。
例えば、擁壁工などの一つの工種も、コンクリート、鉄筋、基礎砕石、型枠、掘削埋め戻しなど、膨大かつ詳細な材料や施工費の集合です。
そうした詳細な数量に対して、それぞれの単価を入れて直接工事費を算出します。
単価の根拠は、建設物価調査会や経済調査会などの公益法人が発行する「建設物価」「土木施工単価」などに拠ります。
発注者は、発注工区の詳細な数量計算書に、公表単価を入れて積算し、直接工事費を算出し、基準に従って間接費を上乗せして、予定価格を確定します。
入札業者側は、発注側の図書(図面、数量計算書)等を受けて、行政と同じやり方で、公表単価を用いて積算し、発注側の予定価格を推定します。
実際の入札額は、他社との競合状況、自社の施工実績(大体が長年の経験での勘)、最低制限価格などを考慮して、確定します。
入札時は、金額のみの入札になります。
日本は、欧米と比べて、発注者、受注者双方において、詳細で、かなりの手間がかかる積算をしています。